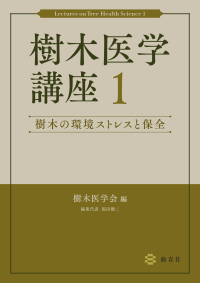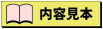|
ご注文について | 書店様へ |

|
| ホーム | 出版目録 | 書評・紹介記事 | 常備店 | リンク集 | English |
|
樹木医学講座1 樹木の環境ストレスと保全
内容紹介シリーズ執筆者120名、学会の総力を結集! 第1巻では樹木の生理的反応やストレス被害のメカニズム、環境ストレスの被害と樹林地の管理、海岸林の機能と管理、各地の希少樹種や絶滅危惧種の保全を取り上げています。
主要目次第1部 樹木の生育環境とストレス応答
樹木の生育環境とストレス応答 (崎尾 均) 1章 雪と樹木 (小野寺 弘道) 1.1 はじめに 1.2 雪の環境 1.3 雪の樹木に及ぼす影響 1.4 雪に対する樹木の適応 1.5 おわりに 2章 土と樹木―樹木の成長を支える微生物の働き― (山中 高史) 2.1 はじめに 2.2 菌根菌とは 2.3 菌根菌の生育と土壌との関係 2.4 おわりに 3章 火と樹木 (津田 智) 3.1 火は樹木にとっての災難か? 3.2 山火事と樹木の生き残り 3.3 草原火入れと樹木 4章 風と樹木 (鈴木 覚) 4.1 はじめに 4.2 風の性質と樹木の応答 4.3 風が成長や樹形に及ぼす影響 4.4 根返りや幹折れはどのように発生するのか 5章 樹木と温度 (小林 誠) 5.1 はじめに 5.2 樹木の生理特性・成長様式・繁殖戦略と温度環境 5.3 樹木の分布と温度環境 5.4 温度環境の変動と樹木の分布 6章 水と樹木 (山本 福壽・岩永 史子) 6.1 はじめに 6.2 根圏の水分欠乏 6.3 根圏の水分過剰 6.4 おわりに 7章 光と樹木 (小池 孝良) 7.1 はじめに 7.2 光の特徴 7.3 光合成作用 7.4 まとめ 8章 樹木の寿命 (勝木 俊雄) 8.1 はじめに 8.2 寿命の定義 8.3 樹木の最高年齢 8.4 樹木の年齢の制限要因 8.5 ‘染井吉野’の最高年齢 第2部 環境ストレスと樹林地の管理 環境ストレスと樹林地の管理 (小池 孝良・池田 武文) 1章 北大札幌キャンパスにおけるハルニレの事例 (小池 孝良) 1.1 はじめに 1.2 キャンパスのハルニレ 1.3 外生菌根菌の役割 1.4 腐朽と風害 1.5 衰退木管理の課題 2章 樹木に対する微小粒子状物質(PM2.5)の影響 (山口 真弘・伊豆田 猛) 2.1 はじめに 2.2 植物に対するエアロゾルの直接影響 2.3 日本の樹木に対するPM2.5の長期暴露実験 2.4 おわりに 3章 都市の環境と樹木のストレス応答 (小田 あゆみ・福田 健二) 3.1 都市環境が樹木に与えるストレス 3.2 高温・乾燥ストレスが引き起こす樹木の障害 3.3 都市環境における樹木の簡便なストレス診断法の検討 3.4 都市環境における植栽管理 4章 天橋立を次世代に引き継ぐための環境整備 (池田 武文・芝原 淳・糟谷 信彦・深町 加津枝・伊藤 武) 4.1 はじめに 4.2 天橋立保全の考え方 4.3 マツ材線虫病対策の現状 4.4 マツ林の状況把握 4.5 おわりに 4.6 現在の取り組み 5章 摩周湖外輪山の樹木減少について (山口 高志) 5.1 背 景 5.2 立ち枯れ地点 5.3 立ち枯れと見えることの解釈について 5.4 大気汚染物質の調査事例 5.5 シカ食害について 5.6 気象要因について 5.7 何をすればいいのか? 5.8 とはいえ金はかけられない 5.9 まとめ 第3部 海岸林の保全 海岸林の保全―海岸林の現在地― (鈴木 覚) 1章 日本の海岸林の成り立ちと推移―庄内海岸林を中心に― (梅津 勘一) 1.1 はじめに 1.2 日本の海岸林成立過程 1.3 海岸林の変遷と課題 1.4 おわりに 2章 海岸林における津波以外の防災機能 (河合 英二) 2.1 海岸林の防災機能 2.2 飛砂防止機能 2.3 海岸林の防風機能 2.4 海岸林の空中塩分捕捉機能 2.5 海岸林の防霧機能 2.6 海岸林の理想的な林帯配置 3章 海岸林の津波被害と津波被害軽減機能 (坂本 知己) 3.1 はじめに 3.2 海岸林の津波被害 3.3 津波に対する海岸林の機能 3.4 津波に対する防災施設としての海岸林の特徴 3.5 おわりに 4章 海岸林におけるマツ材線虫病対策 (中村 克典) 4.1 はじめに 4.2 海岸林におけるマツ材線虫病対策 4.3 松林の衰退要因への対処 4.4 おわりに 5章 広葉樹導入による海岸林の混交林化 (金子 智紀) 5.1 はじめに 5.2 秋田県における広葉樹導入の小史 5.3 広葉樹導入の要点 5.4 広葉樹の成長と導入の限界 5.5 広葉樹をどのように活かすか 5.6 おわりに 6章 海岸防災林復旧・再生の経過と今後の保育管理 ―東日本大震災からの復旧・復興― (林野庁森林整備部治山課) 6.1 はじめに 6.2 現在に至る経過 6.3 各県における取組 6.4 今後の保育管理 6.5 おわりに 第4部 希少樹木の保全 希少樹木の保全 (平尾 知士) 1章 北海道における希少樹木の保全 (植田 守) 1.1 はじめに 1.2 希少樹木の保存と増殖に関する手順 1.3 北海道の希少樹木の林分情報 1.4 北海道の希少樹木サカイツツジ 1.5 北海道特有の樹種シロエゾマツ 1.6 ヤチカンバの保存状況 1.7 おわりに 2章 東北地方における希少樹種の保全 (三浦 真弘・長谷部 辰高・千葉 信隆・織邊 俊爾・竹田 宣明) 2.1 はじめに 2.2 東北育種場における絶滅危惧種の収集・保存状況 2.3 絶滅危惧種、天然記念物のクローン増殖 2.4 馬ノ神岳のカラマツの保全 2.5 陸前高田の奇跡の一本松の保全 2.6 おわりに 3章 関東・中部地方における希少樹木の保全 (生方 正俊・長谷部 辰高・大久保 典久) 3.1 日本にはどのくらい希少樹木があるか 3.2 林木育種センターでの希少樹種保全の取組 4章 近畿・中国・四国地方における絶滅危惧種の保全 (磯田 圭哉・笹島 芳信・岩泉 正和) 4.1 はじめに 4.2 関西育種場における絶滅危惧種の収集・保存状況 4.3 絶滅危惧種の増殖 4.4 トガサワラの保全 4.5 シコクシラベの保全 4.6 おわりに 5章 九州地方における希少樹種ヤクタネゴヨウの保全例 (千吉良 治) 5.1 はじめに 5.2 ヤクタネゴヨウとは 5.3 種の保存に必要な個体数を目標とした生息域外保存 5.4 つぎ木による生息域外保存 5.5 生息域外保存個体間の人工交配による増殖 5.6 屋久島島内での生息域外植栽試験の開始 5.7 おわりに 6章 八重山諸島の希少樹種の保全 (楠城 時彦) 6.1 はじめに 6.2 八重山諸島の植生と植物相 6.3 八重山諸島の希少樹種と保全体制 6.4 希少樹種の増殖と保存 6.5 おわりに 索 引 執筆者紹介池田 武文 京都府立大学名誉教授 伊豆田 猛 東京農工大学大学院 農学研究院 物質循環環境科学部門 磯田 圭哉 森林総合研究所林木育種センター遺伝資源部 伊藤 武 京都府樹木医会 岩泉 正和 森林総合研究所林木育種センター関西育種場 岩永 史子 鳥取大学農学部生物資源環境学科国際環境科学講座 植田 守 森林総合研究所林木育種センター 生方 正俊 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場 梅津 勘一 樹木医事務所「明翠舎」 近江澤 利美 森林総合研究所森林保険センター保険総務部 大久保 典久 森林総合研究所林木育種センター九州育種場 小野寺 弘道 山形大学名誉教授 織邊 俊爾 森林総合研究所林木育種センター東北育種場 糟谷 信彦 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 勝木 俊雄 森林総合研究所九州支所 金子 智紀 秋田県林業労働対策基金 河合 英二 元・森林総合研究所 小池 孝良 北海道大学名誉教授 小林 誠 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ 坂口 智大 林野庁 森林整備部 治山課 坂本 知己 元・森林総合研究所 崎尾 均 新潟大学名誉教授 笹島 芳信 森林総合研究所林木育種センター東北育種場 芝原 淳 京都府農林水産技術センター農林センター森林技術センター 鈴木 覚 森林総合研究所森林災害・被害研究拠点 竹田 宣明 森林総合研究所林木育種センター東北育種場 多田 賢二 林野庁四国森林管理局香川森林管理事務所 田中(小田)あゆみ 信州大学学術研究院(農学) 千吉良 治 森林総合研究所林木育種センター九州育種場 千葉 信隆 秋田県林業研究研修センター 津田 智 岐阜大学流域圏科学研究センター 中村 克典 森林総合研究所東北支所 楠城 時彦 森林総合研究所企画部 長谷部 辰高 森林総合研究所企画部 平尾 知士 森林総合研究所林木育種センター育種部 深町 加津枝 京都大学大学院農学研究科 福田 健二 東京大学大学院農学生命科学研究科 三浦 真弘 森林総合研究所林木育種センター指導普及・海外協力部 山口 高志 エネルギー・環境・地質研究所(北海道立) 山口 真弘 長崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科 環境科学領域 山中 高史 森林総合研究所東北支所 山本 福壽 智頭の山人塾
|