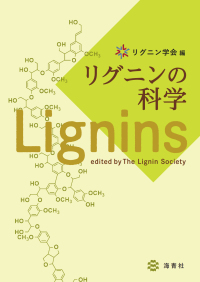|
ご注文について | 書店様へ |

|
| ホーム | 出版目録 | 書評・紹介記事 | 常備店 | リンク集 | English |
リグニンの科学
内容紹介本書はリグニン学会の情報発信の一環として、リグニンに関する学術および科学技術、すなわち化学、組織化学、物理特性、生化学と分子生物学、利用技術、分析技術などについて2024年までの知見を取りまとめたものである。リグニン科学分野のみならず、広くリグニンに関わる諸分野の研究者および技術者、大学院および大学学部および高等専門学校学生等の参考に資することを目指した。
主要目次序章 定義と概観 (梅澤俊明)
0.1 リグニンとは 0.2 リグニンに関連する用語の整理 第1章 化学構造と超分子構造 (梅澤俊明) 1.1 はじめに (梅澤俊明) 1.2 リグニンモノマー (梅澤俊明) 1.3 リグニンの化学構造 1.3.1 サブストラクチャー(結合様式) (秋山拓也) 1.3.2 維管束のリグニンの化学構造と植物の系統との関係 (梅澤俊明) 1.3.3 植物個体内におけるリグニンの化学構造の多様性 (梅澤俊明) 1.3.4 裸子植物(針葉樹)、シダのリグニン (秋山拓也) 1.3.5 広葉樹、双子葉植物のリグニン (秋山拓也) 1.3.6 イネ科植物のリグニン (宮本託志) 1.3.7 特定の植物種や器官などに見いだされるリグニン (梅澤俊明) 1.3.8 培養細胞のリグニンの化学構造 (山村正臣) 1.3.9 ストレス応答において合成されるリグニンの化学構造 (梅澤俊明) 1.3.10 組換え植物が作るリグニンの化学構造 (宮本託志) 1.4 LCCの構造 (安藤大将・西村裕志) 1.4.1 LCCとは 1.4.2 エーテル型LC結合 1.4.3 エステル型LC結合 1.4.4 LC結合に関するNMRデータについて 1.5 超分子構造 (河本晴雄) 第2章 組織化学 (福島和彦・吉永 新) 2.1 はじめに (福島和彦) 2.2 シロイヌナズナのリグニン 2.2.1 シロイヌナズナのリグニン分布 (吉永 新・松井直之) 2.2.2 シロイヌナズナの木化 (吉永 新) 2.3 針葉樹および広葉樹のリグニン 2.3.1 針葉樹および広葉樹のリグニン分布 (吉永 新・松井直之) 2.3.2 針葉樹および広葉樹材の木化過程 (吉永 新) 2.3.3 細胞壁の部位ごとの特徴 (福島和彦) 2.4 単子葉植物のリグニン 2.4.1 単子葉植物のリグニン分布 (吉永 新・松井直之) 2.4.2 単子葉植物の木化 (吉永 新) 第3章 物理的性質 (古田裕三) 3.1 はじめに (古田裕三) 3.2 密度・微細空隙・水分等吸着特性への寄与 (神代圭輔) 3.2.1 密度への寄与 3.2.2 微細空隙への影響 3.2.3 水分等吸着特性への寄与 3.3 力学的性質・熱的性質・粘弾性的性質 (三好由華) 3.3.1 木材構成成分の熱軟化特性 3.3.2 木材の熱軟化特性 3.3.3 リグニンの熱力学的状態 3.4 その他の物理的性質への寄与 (久保智史) 3.4.1 木材の強度特性への寄与 3.4.2 木材およびその成分の劣化に対する寄与 3.4.3 単離リグニンの熱分解と木材の炭素化への寄与 3.4.4 単離リグニンの物理特性 3.5 木材の加工・利用に関する技術への寄与 (田中聡一) 3.5.1 木材物性による理解 3.5.2 木材の乾燥 3.5.3 木材の流動成形 第4章 生合成と代謝工学 (梶田真也・光田展隆) 4.1 はじめに (梶田真也) 4.2 生合成経路 4.2.1 芳香族アミノ酸経路 (木村(武田)ゆり・横山 諒) 4.2.2 ケイ皮酸/モノリグノール経路 (梅澤俊明) 4.2.3 標準モノリグノール以外のモノマーの生合成 (梅澤俊明) 4.2.4 モノリグノールの貯蔵と輸送 (津山 濯) 4.3 モノリグノールの重合と高分子化 4.3.1 リグニンモノマーの重合を触媒する酵素 (飛松裕基) 4.3.2 モノリグノールの脱水素重合と主要な結合様式の生成 (秋山拓也) 4.3.3 リグニンの高分子化 (松下泰幸) 4.3.4 立体異性 (秋山拓也) 4.4 リグニン多糖複合体の形成機構 (西村裕志) 4.4.1 αエーテル:ベンジルエーテル型(BE)LC結合の形成機構 4.4.2 αエステル:ベンジルエステル型 LC結合、γ -エステル型LC結合の形成機構 4.4.3 フェニルグリコシド型(PhGly)LC結合の形成機構 4.4.4 アセタール型LC結合の形成機構 4.5 転写制御 (光田展隆・坂本真吾) 4.6 その他の制御 (光田展隆・坂本真吾) 4.7 代謝工学 (光田展隆・坂本真吾) 4.8 リグニンの含有量や分子構造が変化した突然変異体 (梶田真也) 4.8.1 双子葉植物の変異体 4.8.2 イネ科植物の変異体 4.8.3 木本植物の変異体 第5章 化学反応性 (横山朝哉) 5.1 はじめに (横山朝哉) 5.2 酸性下における反応 (横山朝哉) 5.2.1 ベンジルカチオン構造の生成反応 5.2.2 β-O-4構造の反応 5.2.3 その他の構造の反応 5.2.4 酸性下における化学パルプ化反応 5.3 アルカリ性下における反応 (横山朝哉) 5.3.1 フェノール性部分の反応 5.3.2 非フェノール性部分の反応 5.4 酸化分解 (横山朝哉) 5.4.1 酸素酸化 5.4.2 過酸化水素酸化 5.4.3 二酸化塩素酸化 5.5 還元(選択水素化)分解 (中川善直) 5.6 電気分解 (髙野俊幸) 5.6.1 電解反応 5.6.2 リグニンのEMS酸化 第6章 熱化学反応性 (河本晴雄) 6.1 はじめに (河本晴雄) 6.2 熱重量分析 (河本晴雄) 6.2.1 熱分解生成物と一次および二次熱分解 6.2.2 リグニン熱重量減少挙動の特徴 6.2.3 複合型熱分析 6.3 熱分解反応 (河本晴雄) 6.3.1 熱分解温度と生成物の化学構造 6.3.2 フェニルプロパン側鎖で起こる熱分解反応(400℃以下) 6.3.3 ベンゼン環の開裂・ガス化とPAH生成(400℃以上) 6.3.4 炭 化 6.3.5 多糖成分との相互作用 6.4 超臨界流体中での反応 (南 英治) 6.4.1 超臨界流体 6.4.2 超(亜)臨界流体中でのリグニンの分解 6.4.3 超臨界流体技術の応用 6.5 酸化・燃焼反応 (河本晴雄) 6.5.1 リグニンの燃焼過程 6.5.2 リグニンの燃焼特性 6.6 理論化学による解析 (細谷隆史) 6.6.1 フェネチルフェニルエーテルの熱分解 6.6.2 リグニン中の主要結合の結合解離エネルギー 第7章 生分解 (河合真吾) 7.1 はじめに (河合真吾) 7.2 木材腐朽菌によるリグニン分解 7.2.1 白色腐朽菌の特長 (平井浩文・森 智夫・亀井一郎) 7.2.2 リグニン分解酵素類の詳細 (平井浩文・森 智夫・亀井一郎) 7.2.3 植物の進化に合わせた木材腐朽菌の変遷 (堀 千明) 7.3 細菌によるリグニン分解 (政井英司・上村直史) 7.3.1 β-O-4、β-5、β-1、5-5、β-β型二量体等の代謝経路 7.3.2 脱メチル化システム 7.3.3 芳香環開裂経路 7.3.4 代謝系遺伝子の転写制御 7.4 シロアリによるリグニン分解 (板倉修司) 7.4.1 シロアリの消化管でのリグニン分解様式 7.4.2 シロアリ消化管内でのリグニン分解に関わる酵素 第8章 生理機能と環境応答 (小林 優) 8.1 はじめに (小林 優) 8.2 形態形成とリグニン 8.2.1 木部における役割 (光田展隆) 8.2.2 微小領域の木化 (光田展隆) 8.2.3 カスパリー線 (神谷岳洋) 8.2.4 あて材形成 (吉永 新) 8.3 土壌中のリグニン関連物質 (渡邉 彰) 8.3.1 腐植形成におけるリグニンの寄与とリグニン由来成分の機能 8.4 リグニンの生理活性 (山村正臣) 8.5 植物のストレス応答とリグニン 8.5.1 感染応答 (川崎 努・横田信三) 8.5.2 非生物ストレス応答 (佐藤 康) 8.6 栄養条件とリグニン蓄積 (小林 優) 8.6.1 窒素供給の影響 8.6.2 ホウ素供給の影響 8.6.3 ケイ素供給の影響 第9章 利 用 (山田竜彦) 9.1 はじめに (山田竜彦) 9.2 高分子材料としての利用 9.2.1 アルカリ蒸解からの工業リグニン (山田竜彦) 9.2.2 加溶媒分解からの工業リグニン (浦木康光・野中 寛・山田竜彦) 9.2.3 リグニンスルホン酸塩の特徴と利用 (相見 光) 9.2.4 加水分解からの工業リグニン (山田竜彦) 9.2.5 接着剤としての利用 (梅村研二) 9.3 有用モノマーの生産と利用 9.3.1 化学変換によるモノマー生産とその利用 (宮藤久士) 9.3.2 生物の機能を利用した有用物への変換(Biological funneling)とその利用 (大塚祐一郎) 9.4 エネルギー源としてのリグニン含有物の利用 (岩崎 誠) 9.4.1 木材(バイオマス)のペレット化と半炭化 9.4.2 製紙工場での黒液の燃焼によるエネルギーの利用 9.4.3 黒液のガス化 9.4.4 黒液からリグニン分解物の抽出と燃料としての利用 第10章 試料調製 (岸本崇生) 10.1 はじめに (岸本崇生) 10.2 モデル化合物の合成 (岸本崇生) 10.2.1 単量体 10.2.2 二量体 10.2.3 β-O-4型ポリマー 10.3 モノリグノールの脱水素重合 (幸田圭一) 10.3.1 はじめに 10.3.2 DHP調製研究の歴史的背景とその意義 10.3.3 混合法と滴下法によるDHPの調製 10.3.4 透析膜法によるDHPの調製 10.3.5 DHPオリゴマーからのジリグノールの単離 10.3.6 DHPをめぐるその他のトピック 10.4 リグニンの単離 (西村裕志) 10.4.1 Milled Wood Lignin(MWL)の調製方法 10.4.2 リグニン抽出の前処理としての微粉砕方法、酵素処理 10.4.3 LCC(Lignin Carbohydrate Complex)の調製方法 第11章 可視化法 (福島和彦) 11.1 はじめに (福島和彦) 11.2 可視化の歴史 (髙部圭司) 11.2.1 モイレ反応およびフロログルシン塩酸反応 11.2.2 紫外線顕微鏡法 11.2.3 過マンガン酸カリウム(KMnO4)染色法 11.2.4 オートラジオグラフィー 11.2.5 蛍光顕微鏡法 11.2.6 リグニンの臭素化-SEM-EDAX法 11.2.7 リグニンスケルトン法 11.2.8 免疫標識法 11.3 分布の可視化 11.3.1 呈色反応 (粟野達也・髙田昌嗣) 11.3.2 特殊光学顕微鏡法 (髙部圭司) 11.3.3 免疫標識法 (吉永 新) 11.3.4 分光分析法(1)(蛍光顕微鏡法) (吉永 新) 11.3.5 分光分析法(2)(顕微ラマン分光法) (吉永 新) 11.3.6 蛍光特性を活用したリグニン分布観察 (飛松裕基) 11.3.7 質量分析イメージング (青木 弾) 11.4 酵素分布・代謝物質の輸送過程の可視化 11.4.1 DAB染色 (粟野達也) 11.4.2 標識タグ付きモノリグノールを用いた木化の蛍光イメージング (飛松裕基) 11.4.3 光顕オートラジオグラフィー (福島和彦) 11.4.4 電顕オートラジオグラフィー (髙部圭司) 第12章 定量法 (松下泰幸) 12.1 はじめに (松下泰幸) 12.2 重量法による定量 12.2.1 クラーソン法 (松下泰幸) 12.2.2 チオグリコール酸重量法 (津山 濯) 12.3 吸光分析による定量 12.3.1 チオグリコール酸法 (山村正臣) 12.3.2 アセチルブロマイド法 (杉元倫子) 12.4 赤外および近赤外分光分析による定量 12.4.1 赤外分光分析法 (堀川祥生) 12.4.2 近赤外分光分析法 (服部武文・山村正臣) 12.5 パルプの残存リグニン (友田生織) 12.5.1 Kappa価法 12.5.2 塩素消費量法(Cl価法) 12.6 細胞壁結合型ケイ皮酸類の定量 (宮本託志) 12.6.1 アルカリ加水分解法 12.6.2 その他の方法 第13章 構造解析法 (秋山拓也) 13.1 はじめに (秋山拓也) 13.2 化学分解法 13.2.1 アシドリシス (秋山拓也・横山朝哉) 13.2.2 チオアシドリシス (斎藤香織) 13.2.3 ニトロベンゼン酸化 (秋山拓也) 13.2.4 酸化銅酸化 13.2.5 メチル化過マンガン酸カリウム酸化 13.2.6 DFRC 13.2.7 TIZ法とγ-TTSA法 (安藤大将) 13.2.8 オゾン酸化 (秋山拓也) 13.2.9 メトキシ基定量法(HI法) 13.3 分析的熱分解法 (中川明子) 13.4 ミクロスケール法 (山村正臣) 13.5 NMR法 13.5.1 1H-NMR (秋山拓也) 13.5.2 13C-NMR (岸本崇生) 13.5.3 二次元NMR (秋山拓也) 13.6 分子量 (久保智史・髙橋史帆・髙田依里) 13.6.1 単離リグニンの溶解性 13.6.2 GPCによる単離リグニンの分子量測定 13.6.3 GFCによる単離リグニンの分子量測定 略号表 索 引 執筆者紹介(*:章編者)相見 光 (日本製紙) 青木 弾 (名古屋大) 秋山拓也 (東京大)* 粟野達也 (京都大) 安藤大将 (秋田県大) 板倉修司 (近畿大) 岩崎 誠 (MIPコンサル) 梅澤俊明 (京都大)* 梅村研二 (京都大) 浦木康光 (北海道大) 大塚祐一郎 (森林総研) 梶田真也 (東京農工大)* 松井直之 (森林総研) 上村直史 (長岡技科大) 亀井一郎 (宮崎大) 河合真吾 (静岡大)* 坂本真吾 (産総研) 岸本崇生 (京都大)* 木村ゆり (山形大) 久保智史 (森林総研) 神代圭輔 (京都府大) 幸田圭一 (北海道大) 河本晴雄 (京都大)* 小林 優 (京都大)* 斎藤香織 (京都大) 杉元倫子 (森林総研) 佐藤 康 (愛媛大) 髙田依里 (森林総研) 高橋史帆 (森林総研) 髙田昌嗣 (愛媛大) 高野俊幸 (京都大) 友田生織 (王子HD) 髙部圭司 (京都大) 田中聡一 (京都大) 津山 濯 (宮崎大) 飛松裕基 (京都大) 中川善直 (東北大) 中川明子 (筑波大) 西村裕志 (京都大) 堀 千明 (北海道大) 野中 寛 (三重大) 服部武文 (徳島大) 平井浩文 (静岡大) 福島和彦 (名古屋大)* 古田裕三 (京都府大)* 細谷隆史 (京都府大) 政井英司 (長岡技科大) 堀川祥生 (東京農工大) 森 智夫 (静岡大) 神谷岳洋 (東京大) 松下泰幸 (東京農工大)* 光田展隆 (産総研)* 南 英治 (京都大) 宮藤久士 (京都府大) 宮本託志 (新潟大) 三好由華 (森林総研) 川崎 努 (近畿大) 山田竜彦 (森林総研)* 山村正臣 (徳島大) 横田信三 (宇都宮大) 横山朝哉 (東京大)* 横山 諒 (マックスプランク研) 吉永 新 (京都大)* 渡邉 彰 (名古屋大)
|